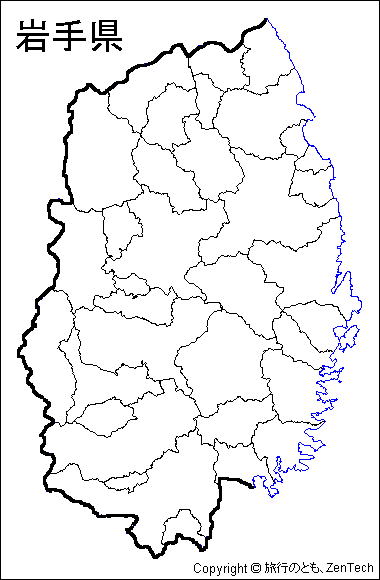
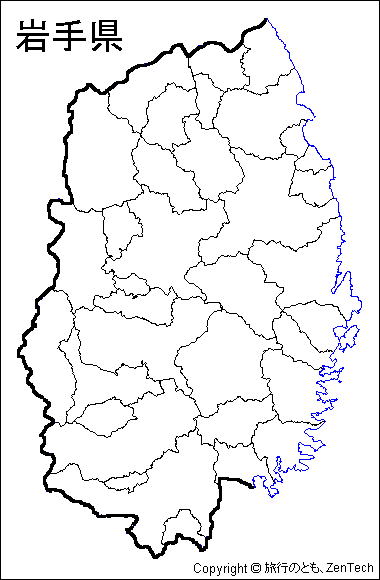
羽場城
| 羽場城 山地 場所 羽場村 城主 舞草内匠 本丸 四十五間(82m) 三十八間(69m) 二ノ丸 廿九間(34.5m) 四十間(72.7m) 1間は約1.8182メートルに相当として計算 |
舞草内匠は三千石を領したる 東磐井郡母体村 先祖累代明細書より |
原典 奥州領葛西臣家(家臣)居城之傅記 文久元年三月十八日(1860) 気仙沼新町下小路 加藤右衛門 |
引用文献 東北歴史資料館(編) (1990). 解読 葛西家文書 資料集28 東北歴史資料館 p.20. |
| 羽場城山 場所 羽場村 此城主 舞草内匠と申候 本丸 東西四十五間 南北三十八間 二ノ丸 東西三十九間 南北三十間 |
上の資料とは二ノ丸の数字が微妙に異なっている | 東磐井郡誌 臨川書店 復刻昭和61年(初版大正14年) p.178 | |
| 羽場館 位置 岩手県前沢町生母字羽場 「県道河東線赤津蓑輪地区から北、新田下を北上方面に下りたところに羽場の部落がある。ここに東西130m位、南北約70mの台地があるが、ここが羽場館跡といわれている。」(前沢町史 中巻 1976, p.263) 岩手県前沢町生母字羽場は現在の岩手県奥州市前沢区生母羽場 |
「『赤生津村風土記』にもこの名は出ないが、土地の伝承によると館跡とされている。荒谷屋敷大石家に、享保十六年(1731)に描いた赤生津、目呂木両村の『谷起紛争調停絵図』が保存されている。これは北上川中州の所有で、多年激しく争ったため、肝入立ち会いのもとに大肝入が縄を引き、境を新しく設定した『絵図面』である。この時、縄を引く基点の1つに『羽場館』がある。」(前沢町史 中巻 1976, p.263) | 引用文献 前沢町史編集委員会 (1976). 前沢町史 中巻 岩手県胆沢町前沢町教育委員会 |
|
| 羽場城主 舞草内匠胤長 | 天正19年 須江山の変(深谷の難)の犠牲者の名前の中にあり。 | 風雲小野寺一族p.177 |
文献で羽場城主が葛西家家臣の舞草内匠であることは確かなようだ。羽場城は現存していない。小野寺家文書が示すように舞草内匠が深谷の難で謀殺されたとするなら、羽場城は天正19年(1591)ごろまでは存在していたことになる。羽場城が住居用だったのかも不明だが、城主を失った城がその後取り壊されたのかもしれない。いずれにせよかなり早い時期に消滅していたのであろう。
舞草内匠がどのような人物かは不明だが、風雲小野寺一族には舞草内匠胤長と記されている。胤長の胤という字は千葉姓に多いように思うので、葛西家家臣で千葉系統の城主だったのかも知れない。
